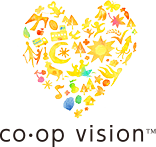事業報告
2024年度の振り返り
3つの柱の実現に向けたおもな取り組み
3つの柱 1.お買い物を通じたくらしの安心づくりをすすめます
すべての地域・世代で利用しやすい宅配を起点とした買い物サービスの実現
お買い物を通じた、地域との交流・地域課題の解決
「宅配事業」から「買い物支援事業」への変革をすすめました
- 週一宅配を軸にその他のサービスを組み合わせた買い物支援をすすめています。第1段階として、買い物送迎車「買いもん行こカー」は、全32台(37店舗へ送迎)の車両管理を、店舗から協同購入センターへ移管しました。
- 夕食サポート「まいくる」は、お届けエリアの拡大をめざし、各協同購入センターへ「まいくるセンター(配送拠点)」の設置をすすめ、全協同購入センターにひろがりました。
店舗めーむひろばの活性化をすすめました
- 店舗利用の組合員に『めーむ』の魅力を伝える「めーむひろばフェア」を開催。宅配・店舗の両事業の連携により、計画を大きく上回る3025人の申し込みを受け付けました。
地域やくらしに合わせた『めーむ』づくりに取り組みました
- 組合員、職員が地元商品を学習し、『めーむ』紙面の企画に参加する「地域めーむ会議」を開始。第6地区の地域コープ委員会が稲美町にある「コープこうべ商品 ひね酢」の工場を取材し、8月2回『めーむ』に掲載しました。
- 1月に「阪神・淡路大震災30年特別号」を企画しました。また、ローリングストック商品がいつでも購入できるWEBページも開設。「みんなで備える防災」をテーマに、防災意識を持つきっかけづくりに取り組みました。
行政との連携などによる子育て支援に取り組みました
- 神戸市と締結した「子育てしやすい環境づくりに向けた連携協定」に基づき、4月から児童館に来館した0歳児の子育て世帯に、コープこうべの提供する育児用品がプレゼントされる取り組みが始まりました。
- 5月から高砂市、6月から西脇市、10月には芦屋市でも子育て支援の取り組みを開始し、行政と連携して出産祝い品などの提供を行う取り組みは9市にひろがりました。
- 1月から、協同購入センター宝塚・協同購入センター須磨で、家庭から出る「廃食油」を回収し、リサイクルする取り組みを試験的にスタート。リサイクルによって生み出された収益は、出産祝い品提供などの子育て支援に活用します。
行政や地域との協働による買い物支援に取り組みました
- 4月に宍粟市および一般社団法人波賀にこにこマートと「宍粟市波賀町地域買い物支援『小さな拠点』協力に関する覚書」を締結しました。住民有志が運営するスーパー「波賀にこにこマート」の商品調達に協力するとともに、「地域めーむひろば」も開始。買い物困難地域のくらしを応援する、新たなしくみづくりをすすめています。
- 兵庫六甲農業協同組合(JA兵庫六甲)と締結した「持続可能な地域社会づくりに向けた包括連携協定」に基づく取り組みとして、7月、JA兵庫六甲御影支店に「地域めーむひろば」を開設しました。
- 8月から、豊岡市社会福祉協議会などと協働し、福祉施設の送迎車両の空き時間を活用した「地域買いもん行こカー」の運行を開始。豊岡市北部の中竹野コミュニティが月1回コープデイズ豊岡へ送迎し、連携して買い物支援と見守りに取り組んでいます。
- 第4地区では、行政と連携した取り組みとして、三木市が主催する「いきいき体操」開催場所で、移動店舗体験会を行いました。買い物困難地域の課題解決に向け、協議を継続しています。
地域団体や行政と高齢者などの見守りに取り組みました
- 「神河町における買物困難者等への支援に関する協定」に基づき、試験運用をすすめていた、神河町社会福祉協議会との協働による配食が本格スタートしました。見守りを兼ね、夕食サポート「まいくる」を1回平均40食お届けしています。
- 加古川市と締結した「地域活性化に関する包括連携協定」に基づく取り組みとして、1月から、地域担当が使用する業務用端末に、同市が取り組む「みまもりアプリ」をインストールし、高齢者や子どもの「見守りボランティア」に協力しています。
<2025年度に向けて>
多様化する組合員のニーズに合わせた買い物支援の取り組みをさらにひろげます
- 地域ごとに異なる買い物環境を踏まえ、週一宅配を軸に、夕食サポート「まいくる」や買いもん行こカー等を組み合わせたサービスの提供をすすめます。
- デジタルとアナログの融合により、それぞれの地域や組合員一人ひとりに向き合った商品・サービス・情報を提供し、宅配ならではの品ぞろえを実現します。
食料品を中心とした魅力ある店舗の実現
組合員の声・データをもとにした、より便利で楽しいサービスの提案
組合員ニーズや地域性に配慮した品ぞろえ・売り場づくりに取り組みました
- 8月30日に改築オープンしたコープ伊丹では、コープ商品の割合を約40%に高めるとともに、駅前の店舗として総菜の品ぞろえを充実させています。また、コープ伊丹つどい場「COCOROBA」では、地域コープ委員会やコープサークルが中心となり、さまざまな世代の方が参加できるマルシェを開催する等、福祉をテーマとした活動が始まりました。
- より買いやすく、食卓をイメージしやすい売り場の「モデル店舗」として、9月27日にコープ神吉、10月25日にコープ西宮東を改装オープンしました。洋風メニューの提案や旬の果物を使用した店内加工のスイーツなどを品ぞろえし、「豊かな食卓(メニュー)提案のお店」として売り場づくりをすすめました。
- コープめふ・コープ長田では、冷蔵・冷凍機器の入れ替えに合わせて、一部の売り場に「モデル店舗」の考え方に基づく売り場づくりを行いました。
ブランドリニューアルした「コープこうべ商品」のお知らせ・おすすめに取り組みました
- 4月にコープこうべのオリジナル商品を「コープス」から「コープこうべ商品」にリニューアルしました。組合員・職員の投票で新しいロゴマークを決定。環境に配慮し、旧包材を使い切った商品から、パッケージを切り替えています。機関紙 『きょうどう』やホームページ、宅配や店舗でのお知らせ、コープこうべアプリでのスタンプラリー等、認知度をひろげる取り組みを行いました。
- 7月には「コープこうべ商品の魅力、再発見!!」をテーマに「ラブコープフェスタ」を開催。300人以上の組合員・職員が参加し、コープこうべ商品・コープこうべフードプランの学習や試食、交流を通じ、商品の理解を深めました。
- 10月から、職員が学習したコープこうべ商品を店舗の売り場で紹介する「ラブこうべ」の取り組みを始めました。宅配では、2月から学習と試食を行い、組合員へ伝える取り組みをすすめました。
- 「食の備えBOSAI(ぼうさい)ブックvol.1」を作成。ローリングストックの紹介や災害時におすすめのコープ商品、レシピを提案しました。
より便利なサービス提供に向け、利用状況の分析・活用をすすめました
- 宅配や店舗、共済など、事業別の利用状況を統合して分析できるしくみの検討をすすめ、『めーむ』の企画などで試験運用を始めました。
<2025年度に向けて>
「豊かな食卓(メニュー)提案のお店」をめざした売り場づくりをすすめます
- シーアの改装に取り組み、「モデル店舗」として買いやすく、食卓をイメ-ジしやすい売り場に磨きをかけます。また、成功事例を他の店舗へもひろげ、売り場の魅力向上をすすめます。
大規模地震・感染症等の非常時でも商品を提供できる体制の構築
万一の場合の保障を通じた「くらしの安心」の提供
大規模地震などの非常時に備え、訓練・しくみづくりをすすめました
- 「大規模地震の発生を想定した「事業継続計画(※)の検証訓練」や、非常時に役職員の安否状況を把握するための「安否確認訓練」を行いました。
- 行政からの要請に対して適切に対応できるよう、神戸市と「緊急時における生活物資確保に関する協定」の見直しをすすめました。
災害に「備える」取り組みをすすめました
- 防災・減災関連の取り組みや、阪神・淡路大震災から30年の歩み等を掲載した「震災30年特設サイト」をホームページに開設しました。
- 1月17日に役職員を対象とした「震災30年鎮魂特別フォーラム」を開催しました。阪神・淡路大震災で犠牲になられた方々への慰霊とともに、「備える」をテーマに、南海トラフ地震に対する備えについての特別講演や、所属で若い世代へ語り継ぐ取り組みの事例報告を行いました。
「くらしの安心」の提供に向け、健康づくりのサポートと保障の提案に取り組みました
- 店舗の共済相談コーナーで、健康測定器を使って骨密度などを測る健康イベントを開催し、組合員の健康づくりのサポートに取り組みました。
- 子会社の株式会社コープエイシスと連携し、コープ共済と団体保険を組み合わせ、一人ひとりのニーズに合わせた保障の提案ができる職員の育成に取り組みました。
<2025年度に向けて>
非常時における体制の強化に取り組みます
- 事業継続計画の検証訓練や見直し等、非常時でも商品を提供できる体制の改善・実行力の向上に取り組みます。
3つの柱 2.いきいきとしたくらし、地域のつながりづくりをすすめます
若い世代をはじめとした、新たな組合員も参加しやすいしくみの構築
グループだけでなく、個人の活動も支援できる体制の構築
コープこうべアプリを活用した、参加しやすい募金のしくみづくりをすすめました
- 6月にアプリでできるたすけあいとして、コープこうべアプリの「コープTOUCH」に、ポイントで募金ができる機能を追加。ガザ地区の人道支援やコープこうべの奨学金などへの募金を呼びかけ、のべ1万57人が参加し、約200万円の善意が集まりました。
地域の学生・若者との交流・活動がひろがりました
- コープこうべの活動への参加をきっかけに、学生の活動グループが結成され、各地区のイベント取材や「おすすめコープ商品大試食会」「震災の記録をたどる旅」を企画。地域を越えて若者同士が交流し、活動がひろがりました。
個人の活動を支援するしくみづくりをすすめました
- 個人の活動を支援するしくみ「デバンダス.net(※)」の運用を開始。さくら地域コープ委員会では、「デバンダス.net」に登録している講師を招き、コープ桜が丘で学習会を開催。地域の組合員約60人が参加しました。
<2025年度に向けて>
誰もが参加できる活動や取り組みをすすめます
- 募金の使途をわかりやすく組合員にお知らせし、誰もが気軽にできるポイント募金の発展と、活動への参加につながるしくみづくりに取り組みます。
地域課題の解決に向けた、多様な協働プロジェクトの創出
地域が必要とするコミュニティ機能を持った新たな活動拠点づくり
「地域つながるミーティング」をきっかけとした活動がひろがりました
- 「地域つながるミーティング」は、100を超える会場で開催。のべ3441人が参加し、さまざまなテーマで地域がつながりあえる場となっています。
- コープ東豊中では、「地域つながるミーティング」をきっかけに、UR都市機構主催のイベントに出展。ちりめんに混ざった小さな生き物を探す「ちりめんモンスター」を実施し、多くの子どもたちで賑わいました。
- コープ白川台では、「賑わいのある地域にしたい」との声から、イベントを開催。コミュニケーション麻雀や介護美容体験などで多世代が交流しました。
- コープ稲美では、地域の方々とともに近隣の子育て交流施設で「地域つながるピアノコンサート」を開催。稲美町社会福祉協議会による「ふくしのお困りごと相談会」も同時開催し、子どもから大人まで80人を超える方が参加しました。
- コープ上郡では、「子どもを真ん中に」をテーマに、近隣のこども園や学校などと連携し、取り組みをすすめています。9月には、上郡「コープのつどい場 えん」を開設。オープンイベントとして、絵本の読み聞かせや音楽の演奏などを行い、子どもたちの笑顔あふれる交流の機会となりました。
行政との包括連携協定の締結をすすめました
- 4月に宍粟市と「地域活性化に関する包括連携協定」を締結。買い物困難地域のくらしを応援するとともに、子育て支援や障がい者支援の取り組み、高齢者支援など、持続可能な社会の実現をめざし、さまざまな分野で連携します。
- 6月に三木市と「地方創生に関する包括連携協定」を締結し、新たに移動店舗の運行を始めました。健康増進や子育て支援、防災・減災などにも取り組み、地域社会の発展や住民サービス向上などをめざします。
- 3月に三田市と包括連携協定を締結しました。買い物支援や地域・暮らしの安全・安心など幅広い分野で、地域の活性化や持続可能な地域社会の実現、くらしを向上させる取り組みをすすめます。
- 行政や地域諸団体と締結した「包括連携協定」は、11市2町2団体にひろがりました。
行政・団体と連携し、居住支援の取り組みをすすめました
- 困難を抱える女性や子どもを支援する「認定NPО法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ」、学生・留学生をサポートする「公益財団法人 神戸学生青年センター」がすすめるプロジェクトに協力しています。コープこうべは、休眠施設となっていた旧女子寮を提供。住まいの確保が困難な女性向け共同住宅「六甲ウィメンズハウス」が6月にオープンしました。
- 尼崎市の市営住宅を活用した居住支援とコミュニティづくりのネットワーク「REHUL(リーフル)」の輪をひろげています。新たに3団体が加わり、23団体が連携して、地域のつながりづくりや困難を抱えた方々の住まいづくり、居場所づくりに取り組んでいます。
子ども食堂やコミュニティ食堂の支援をすすめました
- 神戸市社会福祉協議会と締結した「こどもの居場所づくり推進協定」に基づいて、神戸市・神戸市社会福祉協議会に集まった寄付物品を、市内の店舗・協同購入センターで、のべ271の子ども食堂へお渡ししました。
新たなつどい場づくりに取り組みました
- 営業終了したコープ東加古川の向かいに、セルフ受け取り方式の「めーむひろば」を併設した、東加古川コープのつどい場「虹」を4月に開設。これまでの活動を継続しながら、新たなつながりもひろがっています。
- 4月にコープデイズ相生に相生「コープのつどい場」を開設しました。オープンイベントには、小学生や「ふれあいひろば コレル相生」で活動している方などが歌やダンスを披露。約500人が来場し、多くの方で賑わいました。
- 西宮市社会福祉協議会、JA兵庫六甲と準備をすすめてきた、西宮市北部のつどい場「みんなほくほく つどい場ばんぶー」は、地域のさまざまな人が出会い、協働できる地域に開かれた交流の拠点として、5月から本格稼働しました。
- 6月には、神戸市西区役所の移転後に空いた玉津庁舎の1階・4階に玉津のつどい場「たまろっと」を開設。コープこうべが神戸市から運営を受託し、地域や行政と連携して幅広い世代が集う地域の交流拠点づくりをすすめています。
- 8月にコープ魚住に魚住コープのつどい場「なきすみ」を開設しました。オープン前に開催されたつどい場ワークショップでは、兵庫県立明石清水高等学校ボランティア部も参加し、地域交流の拠点としての活動について、アイデア出しを行いました。
- 2月には、営業終了したコープ行基の近隣に、コープつどいば「さくら」を開設しました。行基地域コープ委員会やコープサークルをはじめ、地域のさまざまな方が参加できる場づくりをすすめています。
- コープカルチャー西神南閉鎖後の活動支援の場として、2月に西神南「コープのつどい場」を開設。オープンイベントには、多くの方が訪れ、交流を図りました。
コープこうべの施設を活用した取り組みがひろがりました
- コープリビング甲南では、地域の方々が労働者協同組合(※)を設立し、地域に根差す団体が活動する拠点「甲南げんき村」を5月に開設。地域のつながりを育む場をめざし、子どもの学習支援や認知症カフェなど、多世代が交流するさまざまな活動が行われています。
- サービス付き高齢者向け住宅「コープは~とらんどハイム本山」では、併設のコープこうべの保育園「どんぐりっこ もとやま」の園児と、季節のイベントに合わせた作品制作を通じ、多世代交流をすすめました。また、コープサークルや地域とのつながりづくりをすすめ、朗読会やコンサートなども再開しています。
地域課題解決の取り組みをすすめました
- 阪神・淡路大震災を機にひろがったボランティア活動を市民活動として定着させ、互いに助け合う地域社会の形成をめざして設立した公益財団法人コープともしびボランティア振興財団に対し、さらなる地域のボランティア振興の支援として、同財団に1000万円の寄付をしました。
<2025年度に向けて>
地域や支援団体の連携をすすめ多様な課題の解決にさらに取り組みます
- 地域つながるミーティングに新たな参加者を招き、多様な取り組みを生み出します。
- NPO等の支援団体とのネットワークの輪を地域でひろげます。
心とからだの健康維持・向上に向けた活動の場づくり
高齢の方やその家族も含め、みんなが安心して過ごせるサービスの展開
ふれあいひろば(※)を開設し、地域の活動や交流のサポートをすすめました
- コープカルチャー西宮の跡地に「ふれあいひろば コレル西宮」を8月に開設しました。これまでのカルチャー講座の一部が自主運営で活動を開始。交流スペースでは、誰でも気軽に参加できる場づくりをすすめました。
組合員同士の助け合い、支え合いの輪がひろがりました
- 神戸市の「ファミリー・サポート・センター(※)」事業を4月から受託。機関紙『きょうどう』等で広報を行い、新たに協力会員104人、依頼会員537人、協力・依頼会員5人が登録しました。
- 「たすけタッチ(※)」は対象エリアを垂水区・西区・東灘区で拡大する中、7月から兵庫県立舞子高等学校が地域貢献の取り組みとして活動を始めました。
- 助け合い制度「コープむつみ会」は40周年を迎え、これまでの活動を振り返るとともに、「コープむつみ会」への想いを寄せた記念誌を発行しました。今後も心をひとつに、会の発展に取り組みます。
- 「コープくらしの助け合いの会」では、活動をひろげるために説明会やカフェを開催しています。第1地区では、活動会員とコーディネーターが、「ふれあいひろば コレルめふ」の交流スペースを活用し、ふれあいカフェをスタート。地域で活躍する「まちの看護師さん」と連携して、健康相談ができる居場所づくりに取り組んでいます。
認知症や介護を身近に考える機会づくりに取り組みました
- レインボースクールやコープサークルへの学習会などで、介護や高齢者の健康維持に関する学習を推進。レインボースクールでは、39回開催しました。
毎日の健康づくりに取り組みました
- 「ひょうごまるごと健康チャレンジ2024」「おおさかまるごと健康チャレンジ2024」に取り組みました。食事から習慣的に摂取している栄養素量を知るBDHQ調査の結果を読み解く学習会には、のべ179人が参加。食生活による健康づくりをすすめました。
- 第6地区では、朝食をテーマに兵庫県立明石南高等学校調理部がクッキングサポーターと、コープ西明石の店頭でレシピを提案し、世代を越えた学び合いの機会が生まれました。
<2025年度に向けて>
組合員の健康に関する学習や学び合いの活動をひろげます
- 介護に関する学習会やフレイル予防の啓発、スポーツを通じた健康づくり等、組合員の健康づくりに取り組みます。
3つの柱 3.環境や社会のためになる活動・事業モデルを促進します
「エコチャレ2030(※)」の推進を通じ、組合員・地域とともに
環境負荷の低減に向けた取り組みを推進
廃棄物削減・資源循環の取り組みをすすめました
- 玉津のつどい場「たまろっと」に、紙リサイクル機器「玉津ラボ(愛称)」を設置。コープこうべの事業所で使用され、不要となった紙を回収・分別し、コープこうべグループの名刺やオフィス用紙として再生・利用しています。回収・分別作業は特例子会社の阪神友愛食品株式会社、また、機器の操作・製紙作業は地域の障がい者就労支援団体に委託しており、就労支援にもつながっています。
- 宅配で供給した「ラベルレス飲料」1本につき2円を環境保全活動に取り組む団体へ寄付しています。2024年度は合計78万7772円が集まり、11団体へ寄付しました。
ペットボトル回収で地域の環境団体を支援しました
- 一部の店舗に設置している「寄付機能付きペットボトル減容回収機」を通じて回収したペットボトル1本につき1円を環境保全に取り組む団体へ寄付し、活動を支援しています。2023年度に8店舗で集まった50万5973円を6団体に寄付しました。
持続可能なくらしへの理解・実践に向け、学習の機会づくりに取り組みました
- 2024年3月から店舗で出る食品残さの回収・たい肥化業務を外部に委託し、食品リサイクル率の向上に取り組んでいます。5月には、委託先の「たい肥化施設」の見学会を開催し、26人の組合員・職員が参加。廃棄物削減や資源循環について学習しました。
- コープこうべの事業所を中心に、さまざまな施設をめぐり環境の取り組みを学ぶ「夏休み 施設見学会」を開催。鳴尾浜リサイクルセンターや玉津リサイクルセンターの見学など、2回開催し計82人の組合員親子が参加しました。
店舗の食品ロス削減をすすめました
- 9月~11月に「てまえどり」を促進する企画「ハピネスチャージキャンペーン(※)」をコープデイズ神戸西とコープ龍野で行いました。2店舗で6381枚のシールが集まりました。
組合員・職員とともに脱炭素行動の促進をすすめています
- コープこうべが参画する兵庫県の脱炭素アクション「ひょうご1.5℃ライフスタイルコンソーシアム」の企画として、10月から脱炭素行動を促進する取り組み「脱炭素エキデン」を始めました。参加者の二酸化炭素削減量を見える化することで、意識・行動変容を促しています。
<2025年度に向けて>
廃棄物削減や資源循環の取り組みをさらにすすめます
- 紙リサイクル機器「玉津ラボ(愛称)」の活用に地域やコープこうべグループ全体で取り組むとともに、再生された用紙を使ったカレンダー等の開発をすすめます。
持続可能な食と農畜水産業の実現に向けた、生産者・組合員との関係性づくり
組合員・職員・生産者がつながり、相互理解を深めました
- 大阪北地区では、6月に「コープこうべ商品 健太郎トマト収穫体験(神戸市西区)」を開催し、30人の組合員が参加。収穫体験や生産者との交流、神戸市における農業の現状の学習などを通じて、相互理解を深めました。
- 第5地区では、9月に「フードプラン富山県産こしひかり稲刈り体験」を開催し、32人の組合員親子が参加。稲刈りや生産者との交流、JAなんと土づくりセンターの見学を行い、おいしさの秘密を学びました。
- 職員に「CO・OPうなぎ蒲焼」や「コープこうべ商品 えのき茸」などの産地研修を実施。担当部門の職員が参加し、原料や加工などのこだわりを学び、売り場で組合員に伝えました。
- フィリピンミンダナオ島から生産者6人を迎え、シーア組合員集会室で「フレンドリーバナナ学習会」を9月に開催し、26人が参加しました。また、生産者にコープ商品総選挙第1位の記念盾と組合員からの応援メッセージを贈りました。
- 11月の「北海道まつり」に、フードプランの4つの産地から生産者14人が5年ぶりに来訪。売り場で組合員と交流しました。
- 1月に「第2回フードプラン産地交流会」を健保会館で開催しました。「交流(フードプランがつなぐ産地と消費者のきずな)」をテーマに、生産者や取引先、役職員66人が参加。コープこうべフードプランの運用規準となる生協版GAP(※)を学ぶとともに、生産者と意見を交換しました。
持続可能な食の学習や交流の場づくりに取り組みました
- 兵庫県漁業協同組合連合会および兵庫県と3者で取り組んでいる「ひょうご地魚推進プロジェクト(とれぴち)」は10周年を迎えました。7月に「とれぴちフェスタ」を開催し、セリ体験や干しダコづくりなどを通じて、地産地消や食文化の継承、豊かな海づくりへの理解を深めました。また、地域コープ委員会主催のとれぴち学習会など、10周年を記念して、さまざまな企画に取り組み、のべ約2000人が参加しました。
- 環境共生型農園エコファームでは、栽培や収穫体験などの組合員向けイベント、職員や関連団体向けの研修・学習会、学校や外部団体の見学会を開催し、のべ1327人が来園。コープこうべによる環境の取り組みや、子会社の株式会社コープエコファームの持続可能な農業の取り組みを学習しました。
- 大阪北地区では、10周年を迎える「みんなの牧❤里プロジェクト」のさまざまなプログラムを通じて、農業の大変さや楽しさを体験するとともに、毎月、組合員が援農ボランティアとして地元農家との交流を続けています。
<2025年度に向けて>
持続可能な食と農畜水産業について考え、学ぶ活動をひろげます
- 「ひょうご地魚推進プロジェクト(とれぴち)」の魅力を伝える活動をひろげ、豊かな海づくりを組合員とともにすすめます。
- コープこうべフードプランの生産者と組合員・職員の交流を促進します。
障がいのある方が安心して働き、活躍できる場づくり
多様性を受け入れられる職場・環境づくりをすすめました
- 障がい者の雇用率は、コープこうべと、特例子会社の阪神友愛食品株式会社、関連が深い株式会社協同食品センターのグループ適用3社合算で4.60%となりました(3月15日時点)。
- 7月から、障がいのある職員などが抱える接客への不安を和らげるため、希望に応じて「ハートよつばのバッチ」で、個人の特性を周囲に伝える取り組みを開始。37人が着用しています。また、さまざまな職員が「ともにはたらく」組織であることをポスターで組合員にお知らせし、職員の働きやすさと活躍を支援しました。
- 9月と2月に、障がいのある職員を対象とした「十人十色研修」を実施。コミュニケーションスキルを学び、異なる職場で働く仲間との交流を深めました。
- 住吉事務所の事務作業の一部を特例子会社の阪神友愛食品株式会社へ委託し、障がいのある方の実践的な実習の場としても活用しています。2023年4月の取り組み開始以降、障害者就労移行支援事業所から、のべ40人の実習を受け入れました。
- 長年にわたり模範的に仕事に励んできたことを称えられ、店舗と協同購入センターで働く障がいのある職員2人が、一般財団法人兵庫県雇用開発協会理事長表彰を受賞しました。
障がい者支援団体と連携し、就労支援や新たな協働のしくみづくりをすすめました
- 障がい者支援団体との連携による、「めーむひろば」のしくみを活用した就労体験を8カ所で実施し、働くきっかけの場となっています。コープ龍野では、ここで経験を積んだ1人がコープこうべへ就業しました。
- コープリビング甲南では、労働者協同組合や障がい者支援団体と連携し、賞味期限の点検作業などの委託を通じた、新たな就労支援の取り組みをすすめました。
一人ひとりが安心して暮らすことができる社会をめざす社会福祉法人の取り組みを支援しました
- コープこうべが支援して設立された、高齢者や障がい者の福祉施設を運営する社会福祉法人協同の苑に対し、地域における福祉増進にさらに寄与していくために1000万円の寄付をしました。
<2025年度に向けて>
障がいのある方の活躍の場づくりや働きやすい環境づくりをすすめます
- 障がいのある職員の成長や働きがいを高めるため、業務習得の状況を確認し、育成に活用できるツールの作成をすすめます。
社会貢献活動、環境活動への参加者の拡大と取り組み推進
広報・コミュニケーション力強化に向けたしくみづくりと実践
平和の尊さを次世代へ伝える活動に取り組みました
- 平和について学び考えることを目的に、「虹っ子平和スタディツアーin福島」「長崎 平和のカンパ寄贈の旅」「広島平和サイクリングの旅」を実施し、合計21人の中高生が参加。多くの方に伝えるため、学んだことや調べたことを新聞にまとめました。
- 第2地区では、戦禍を経験された地域コープ委員が語り部となり、神戸大空襲などを伝える「平和を考える会」を開催し、中学生にも語り継ぎました。
能登半島の被災地支援に取り組みました
- 令和6年能登半島地震緊急募金を活用し、兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランタリープラザと協働で、大きな被害を受けた石川県珠洲市へのボランティアバスを運行しました。6月に3行程(車中泊含む2泊3日)で実施し、のべ47人の組合員・職員が参加。ガレキ撤去や家具搬出など、片づけ支援活動を行いました。
- コープいしかわへ緊急募金から1000万円を寄付しました。コープいしかわでは、居場所となるカフェ活動などで利用するキッチンカーの購入に活用されました。
- 9月に発生した能登半島豪雨災害の緊急募金には、約416万円の善意が寄せられました。その一部を活用し、コープいしかわの組合員へコープ商品を贈るとともに、アプリ募金で寄せられたメッセージをお渡ししました。
- 被災地への職員派遣は、コープいしかわの業務支援から、日本生協連が設置するコープ被災地支援センターへの派遣に移行し、家財の片づけ等を支援。2024年1月から、のべ60人を派遣しました。
阪神・淡路大震災から30年、防災や減災に取り組みました
- 第2地区では「防災と食物アレルギー」をテーマに、アレルギーの当事者以外にも関心を持ってもらい、有事に備えることの大切さを伝える学習会を6月に開催しました。
- 地域で活動するさまざまな個人や団体同士の「つながり」を通じた持続可能な社会づくりについて考える「地域つながるフォーラム」を9月に開催。「防災」をテーマに、167人が参加しました。
- 震災の記憶を語り継ぐとともに、「防災」の意識を高めることを目的にワーキンググループを発足。組合員有志23人が力を合わせて、1月に命を守る備えを学ぶ学習会「ふだんのくらしに防災を!」を開催し、60人が参加しました。また、2月には、「みんなで楽しむ防災フェスタ」を開催。防災に取り組む9つのグループの活動交流や、落語家の桂吉弥さんによる震災当時を語るプログラムに、約160人が参加しました。
- 1月に第4地区で「そなえて、いのちときもちをまもる」をテーマに「レッツBOSAI!!2025」を開催。50人以上の親子が参加し、日頃から備えることの大切さを考える防災イベントになりました。
「協同の体験を語り継ぐ」取り組みを継続しています
- 生協で働く意義の理解を深める「協同の体験を語り継ぐ」取り組みでは、阪神・淡路大震災の体験を語り合い、職員一人ひとりが「備える」について考えました。
生協で働く意義の理解を深める学習をすすめました
- 生協理念を学ぶ幹部向け研修「賀川豊彦塾」を賀川記念館で開催。賀川豊彦の生涯の軌跡を振り返り、協同組合で働く意義や価値を見つめ直す機会となりました。
子どもが抱える課題への取り組みをすすめました
- 2021年からスタートした「コープこうべの奨学金てとて」は4年目を迎え、11月に88人が奨学生になりました。卒業までの期間、月額1万円の奨学金が給付されます。また、3月には79人が高校などを卒業し、新たな道を歩みはじめました。
- 物価高騰などを背景に、財団の奨学金に応募する学生が増加。奨学生の採用数増加など、さらなる社会貢献に向け、同財団に1000万円の寄付をしました。
- 第2地区では、NPOと連携した「こども支援者のための居場所づくり連続講座」を開催し、活動の支援や活動者同士の交流をすすめました。
広報・コミュニケーションの強化に取り組みました
- コープこうべアプリの「ルーム」やインスタグラムなどのSNSを活用して、地区本部や店舗からイベント情報などの発信を行っています。「ルーム」は43部屋、インスタグラムは48アカウントにひろがりました。
- 組合員自身のインスタグラムでコープの魅力を発信していただく「組合員アンバサダー」の取り組みを1月からスタートしました。第1期として10人のアンバサダーがコープ商品の感想やおすすめポイント等を紹介しています。
- 2月・3月に「コープこうべアプリ登録相談会」を54店舗で実施し、アプリのインストールやコープこうべネットの利用登録、スマートフォンへのコーピーカードの登録をサポートしました。
<2025年度に向けて>
平和や防災・減災、国際協同組合年の取り組みをすすめます
- 国連が国際協同組合年と定めた2025年は、協同組合をテーマに「協同の体験を語り継ぐ」取り組みを継続します。
- 阪神・淡路大震災から30年を迎え、災害に「備える」をテーマに取り組みをすすめます。
- 終戦80年を迎えるにあたって、若い世代とともに「平和」の活動を推進します。
持続可能な経営基盤の確立に向けた構造改革
宅配事業の基盤整備
【取り組み概要】事業環境や社会構造の変化に対応するため、デジタル・運営等の改革とともに、働き方改革に取り組みます
コープこうべアプリの利用拡大とペーパーレス化を推進しました
- 2023年9月のリニューアルで機能を拡充したコープこうべアプリの利用拡大に向け、アプリ利用促進キャンペーンを6月・8月に実施。インターネットでの注文構成比が35.8% (前年差+2.9%)に伸長しました。
- 環境への配慮から、コープこうべアプリのプッシュ通知や『めーむ』の折り込みチラシで、注文用紙が不要な方への配付停止を呼びかけ。19万軒を超える組合員が配付停止の登録をしています。
- 組合員と地域担当の新たなコミュニケーションツールとして、コープこうべアプリで「デジタル版地域担当ニュース」を配信しました。
職員の働きがい・働きやすさの向上に取り組みました
- 猛暑による疲労・熱中症から職員を守り、家族とゆっくり過ごす時間を設けるために、お盆期間の宅配(個人宅配・協同購入グループ・めーむひろば)を休みとする「夏季一斉休業」を導入しました。
- 地域担当が『めーむ』紙面の企画段階から参加し、商品の良さを学び、組合員へ伝える「みんなで利用結集」の取り組みを6回実施。組合員とのコミュニケーションを促進するとともに、職員の働きがい向上をめざしています。
- 職員の働きがいの醸成や、サービス品質の向上を目的とした応対コンテストや交通安全大会を実施しました。
持続可能な事業基盤の構築に向け、コスト低減に取り組みました
- 価格高騰が続くドライアイスの使用基準を精査し、1日当たりのドライアイス使用量を大きく抑制しました(前年比88.4%)。また、さらなるドライアイス削減に向けて、実証実験を行いました。
- 走行距離の短縮による環境負荷低減と、訪問効率の向上による配送コースの最適化を目的に、AIによる配送コース最適化システムを導入し、42区域を削減しました。
「あんしん宅配」の実現に向けた取り組みをすすめました
- 過去の事故を教訓に、無事故への決意と交通事故抑制の手順を確認するセンター長会議を年2回実施。センター長が中心になって、協同購入センター職員一人ひとりへの安全意識の浸透をすすめています。
<2025年度に向けて>
「あんしん宅配」に向けた取り組みのさらなる推進が課題と考えています
- 組合員から信頼される「あんしん宅配」の実現に向けて、「安全運転」「コンプライアンス」の強化に取り組みます。
店舗事業の構造改革
【取り組み概要】生協店舗としての存在意義(お買い物を通じたくらしの安心)の確立へ向けて、事業構造改革をしっかりとすすめます
研修の強化や育成環境の整備など、人材育成の取り組みをすすめました
- 店舗事業の競争力強化に向けて、新卒店舗専門職員、新卒総合職員、業態間異動職員を研修生として配属。各エリアの主要な店舗に集中して配属し、育成環境を整備するとともに、同世代の職員が複数いる環境で働きやすさの向上を図りました。9~10カ月の研修期間を終え、37人が本配属となりました。
業務の簡素化やツールの導入などによる生産性向上に取り組みました
- コープミニを除く全店舗に「入出金機」を導入し、現金を取り扱う業務を削減しました。
- 物流業界の働き方改革により物流経費が高騰していることから、経費の抑制に向けて、店舗への商品配送の効率化に取り組みました。
営業終了基準に該当する店舗などの今後の方向性を決定しました
- 「2024年度営業終了候補店」に選定したコープ長田、コープ加西、コープ箕面中央の3店舗に加え、営業終了基準に該当する23店舗の利用組合員へ経営状況をお知らせするはがきを送付。買い支えのお願いをするとともに収支改善に取り組みました。
- 組合員の買い支えにより、店舗収支が改善したコープ長田は、営業継続を決定しました。
- コープ加西とコープ箕面中央は、組合員の買い支えをいただいたものの、将来の改善が見通せる収支改善には至らなかったことから、営業終了を決定しました(営業終了日:3月27日コープ加西、2025年5月29日コープ箕面中央)。利用組合員にお知らせはがきを送付するとともに、地域説明会や相談会などを開催し、周辺店舗や宅配などの利用案内を行いました。
- 営業終了基準に該当する23店舗のうち、5店舗で基準を上回る改善となりました。
- 賃貸借契約期間満了に伴い、コープ行基を1月30日に営業終了しました。近隣にめーむひろばの受け取り拠点を兼ねた、コープつどいば「さくら」を開設しました。
「2025年度営業終了候補店」を定め、業績改善に向けた準備をすすめています
- 営業終了基準に該当する店舗のうち、コープ茨木白川、コープ打出浜、コープ兵庫、コープ有野、コープ西鈴蘭台、コープ桃山台、コープ姫路砥堀の7店舗を2025年度の営業終了候補店と定めました。収支改善に向けた取り組みをすすめます。
店舗システムの切り替え準備をすすめました
- 競争力強化や生産性向上をめざし、新しい店舗システムの構築をすすめました。2025年度の導入に向けて、業務プロセスの見直しを実施。システムの開発と並行し、手順書やマニュアルの整備を行いました。
<2025年度に向けて>
将来にわたり継続できる事業の実現に向けた構造改革が課題と考えています
- 店舗システム入れ替えを機に、働き方や業務スタイルを変え、効率化を図るとともに、売り場で完結する業務を増やし、組合員サービスの向上につなげます。
保障事業のチャレンジ
【取り組み概要】コープ共済40周年を契機とした価値の浸透と、共済と保険を組み合わせた「くらしの総合保障」を推進します
「どこでも加入」「共済マイページ」の案内を強化しました
- 場所や時間を問わず、スマートフォンでコープ共済の加入手続きができる「どこでも加入」の案内を強化し、5968件の申し込みを受け付けました。また、「共済マイページ」からできる共済金請求の範囲が拡大されたことなどを加入者へひろくお知らせし、登録件数は13万6423件(前年比122.2%)と伸長しました。
お誕生前申し込み制度ができました
- たすけあいジュニアコースの加入者の輪がひろがったことにより、妊娠中におなかのお子様の加入申し込みを行い、お子様の誕生と同時に保障が開始されるお誕生前申し込み制度ができ、受付を始めました。
組合員のたすけあいを形にしたコープ共済の歴史を学習しました
- コープ共済40周年を機に、改めてコープ共済の価値を理解する機会として、コープ共済の成り立ちからこれまでの歩みを学ぶ学習会を、全職員に実施しました。
<2025年度に向けて>
保障を通じた「くらしの安心」が提供できる体制づくりをすすめます
- コープ共済の価値や取り組む意義を再確認し、役職員全員で「たすけあいの輪」をひろげる推進活動に取り組みます。また、万一の備えとして、共済と保険を組み合わせた「くらしの総合保障」の取り組みをすすめます。
福祉事業の既存事業強化
【取り組み概要】将来にわたって持続可能な事業運営の確立に向けて、さらなる収支改善に取り組みます
収支改善に向け、事業所ごとの課題を明らかにし、利用者の拡大をすすめました
- 訪問介護と通所介護の収支改善に向けて、一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構が開催する管理者育成研修に参加しました。研修で学んだことを生かし、事業所ごとの課題の把握をすすめ、利用者拡大に取り組みました。
介護予防に関する学びの場づくりに取り組みました
- 組合員・職員を対象として、介護予防に関する学びの場づくりをすすめ、介護への関心を高める取り組みを行いました。
人材の定着に向け、コミュニケーション強化に取り組みました
- 新入職員の定着に向けて、入所後1カ月を目途に本部職員による面談を実施。日々の困りごとを中心にヒアリングを行いました。
<2025年度に向けて>
介護事業の安定した経営基盤の確立が課題と考えています
- 介護事業では、職員の介護技術力の向上とともに利用者拡大に向けた取り組みを行うことで、経営基盤の確立をすすめます。
文化事業の再構築
【取り組み概要】学び合い・教え合いの活動の場づくりをすすめるとともに、安定した事業運営に取り組みます
コープカルチャーに代わる、新たな学び合い・教え合い活動の場づくりをすすめました
- 2月末までに、すべてのコープカルチャーが閉鎖。3月末をもってコープカルチャー事業を終了しました。コープカルチャーの跡地に、学び合い・教え合い活動の場を開設しました。コミュニティの維持・発展に向け、それぞれの形でスタートしています。
4月15日開設 神戸西「コープのつどい場」 (旧コープカルチャー神戸西)
8月1日開設 「ふれあいひろば コレル西宮」 (旧コープカルチャー西宮)
2月1日開設 西神南「コープのつどい場」 (旧コープカルチャー西神南 - コープカルチャー協同学苑の跡地は、既存の協同学苑貸室事業へ移行しました。講座は2月1日から約7割の講師が自主運営で継続しています。
- コープカルチャー生活文化センターは、「ふれあいひろば コレルせいぶん」(2025年6月予定)開設に向けて準備をすすめています
芦屋シーサイドテニスは事業所を閉鎖しました
- 社会環境や生活の変化、コロナ禍の影響により会員が減少。さまざまな運営改善を行いましたが、施設の老朽化もあり、3月末をもって事業所を閉鎖しました。閉鎖後はテニス事業者へ賃貸します。
コープスポーツの広報強化と、事業継続に向けた構造改革の準備をすすめました
- 新規参加者の拡大をめざし、『コープステーション』や機関紙『きょうどう』、店舗情報誌への掲載に加え、地域情報誌への折込配布を開始し、広報を強化しました。
- 2025年4月からの料金の改定と教室実施回数の統一など運営方法の見直しに合わせて、教室環境の整備をすすめました
<2025年度に向けて>
コープスポーツの安定した事業運営に取り組みます
- 2025年4月から福祉事業として新たな運営をスタートさせ、安定運用と参加者満足度向上をめざします。
協同学苑の収支改善
【取り組み概要】学習機能の強化や、利用者増加による収支改善に取り組むとともに、今後の方向性の検討をすすめます
収支改善に向け、過去の利用者へのアプローチに取り組みました
- 過去の利用者への架電やメール案内を行い、繁忙期の7月・8月・12月の利用者獲得を重点として取り組みました。宿泊利用で前年比110.2%、レストラン利用で前年比102.7%と利用増加につながりました。引き続き、利用者拡大に向けた取り組みの実施と経費コントロールによる収支改善をすすめます。
- 人件費や光熱費などの増加から10月に宿泊料金を改定しましたが、利用者数は前年度並みで推移しています。素泊まり利用が多いことから、要望に応じた食事の提案でレストラン利用を促進し、収支改善に取り組みます。
協同購入センターを拠点とする安全運転センター分室を設置しました
- 10月、実務に即した安全運転教育の推進や受講者の居住地から近い拠点の設置を目的に、協同購入センター東神戸内に安全運転センターの分室を設置しました。
今後の方向性について、あらゆる可能性を検討して論議ををすすめています
- 宿泊利用、レストラン利用が増加したものの、営業剰余金は約6200万円の赤字で、収支の厳しい状況が続いています。また、開設から34年が経過し施設が老朽化していることから、今後も設備更新や修繕対応などの増加が見込まれます。
- 協同学苑の役割を再確認しながら、史料館や安全運転センターのあり方も含め、あらゆる可能性や選択肢を検討して今後の方向性について論議をすすめています。
<2025年度に向けて>
学習機能の強化と方向性の決定が課題と考えています
- 史料館と並行して生活文化センターを活用し、組合員や職員がコープこうべの理念や協同組合の歴史を学び、語り継ぐ機会を増やします。
- 協同学苑の方向性については、現在担っている学習機能、史料館や安全運転センターなどのあり方の見直しも検討しながら、2025年度中に決定します。
その他事業の取り組み(生産、クレリ、コープでんき)
3月末をもって生産事業を終了しました
- 1988年に設立され、「組合員の声」をもとに自己生産品を製造してきた六甲アイランド食品工場は、3月22日に自己生産品の製造を終了し、3月末をもって生産事業を終了しました。また、六甲アイランド食品工場の製造・管理を受託していた子会社の株式会社コープベーカリーは、2025年6月の解散を予定しています。
食品工場生産品のこだわりを継承する取り組みをすすめました
- 食品工場生産品のこだわりを継承するため、日本生協連との共同開発をすすめました。9月22日に「神戸ハイカラメロンパン」「熟成レーズンロール」「熟成バターロール」の菓子パン主力品3品目が、10月27日に「しっとり絹あつあげ」が、3月23日には「熟成ロイヤル」「なめらか絹とうふ」が日本生協連コープ商品としてデビューし、継承商品は42品目になりました。「神戸ハイカラメロンパン」は、焼型を製造メーカーに譲渡し、発売から72年の想いをつないでいます。
- これまでに日本生協連コープ商品に移行した商品も含め、継承商品に対する「組合員の声」を集め、今後も日本生協連とともに改善に向けた取り組みをすすめていきます。
六甲アイランド食品工場でイベントを実施しました
- 職員向けに「ありがとう!食品工場、最後の工場見学~自己生産スピリットを次世代へ~」を2月に開催。さまざまな部署から55人が参加し、食品工場の製造に対する想いが日本生協連との共同開発商品に引き継がれていることを学びました。また、3月には、「食品工場エンディングイベント」を開催し、2日間で組合員48人が参加しました。
葬祭サービス「クレリ」の広報と、運営の見直しをすすめました
- クレリ葬の認知度向上に向けて、店舗での終活・葬儀に関する相談会やクレリホールの見学会を行いました。
- 今後も、より組合員に寄り添った葬祭サービスを提供するため、クレリの事業提携先である兵庫県葬祭事業協同組合連合会(兵葬連)との業務分担を見直し、コープこうべの仏壇・仏具などの展示場(住吉・明石)を9月末に閉鎖。10月1日に兵葬連が中心となりコープリビング甲南に「クレリ展示場」をオープンしました。
コープでんきを通じ、エネルギーに関する社会課題を学ぶ機会を創出しました
- 「真庭バイオマス発電所バス見学会」(計50人が参加)や、「大阪ガス ガス科学館&由良風力発電所バス見学会」(計48人が参加)を開催し、エネルギーに関する社会課題について学習を深めました。
<2025年度に向けて>
- 葬祭サービス「クレリ」は葬儀の事前相談や終活に関する啓発活動を通じて、葬祭に関する組合員のお困りごとの解決と、安心して葬祭サービスを利用できるよう認知度向上に向けた広報活動に取り組みます。
- コープでんきを通じ、エネルギーに関する社会課題を学ぶ機会を創出します。
ガバナンスの改革
【取り組み概要】事業構造の安定化(構造改革の推進)を最重点課題とした組織体制の確立をすすめます
透明性のある組織、責任の所在が明確な組織をめざしたしくみづくりをすすめました
- これまでに実施した業務組織の編成や運営体制、権限の見直しに合わせて、関連する諸規程を改正しました。
- 契約管理体制の強化に向けて、契約業務の課題とリスクを整理。また、契約書の一元管理をめざし、デジタル化の検討に着手しました。
<2025年度に向けて>
管理体制の強化に向けた取り組みをさらにすすめます
- 適正な機関運営に向けて、諸規程の点検・整備を継続します。
- 契約管理体制の強化に向けて、契約業務(契約書の作成、審査から保管、廃棄までの一連業務)のルールの見直しやデジタル化をすすめます。
【用語解説】
- 事業継続計画…災害、感染症、大事故、突発的な経営環境の変化など、不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順などを示した計画。
- デバンダス.net…自分の得意なこと(例:編み物を教えられる等)を登録することができる人材データベース。地域から寄せられた相談に、その内容にあった人をマッチングする。
- 労働者協同組合…市民や働く人々が自ら出資し、それぞれの意見を反映して事業・経営を主体的に担い、地域に必要とされる仕事を自分たちでつくる協同組合。
- ふれあいひろば…地区本部が運営する活動拠点。活動の登録や相談、貸室利用などができる。学びと出会い、組合員同士の交流づくりをめざす。
- ファミリー・サポート・センター…子育て中の人が、急な用事などで子どもの世話ができない時に、地域の人が応援する、相互援助活動を支える制度。
- たすけタッチ…「ゴミ出し等、ちょっとした困りごとを手助けしてほしい組合員と近くに住む手助けできる組合員をコープこうべアプリでつなぐしくみ。
- エコチャレ2030…2018年に策定した、2030年に向けた環境チャレンジ目標。
- ハピネスチャージキャンペーン…賞味・消費期限が迫り値引きしている商品に貼付した「キャンペーンシール」を集めて提出。シール1枚につき1円分の食品を子ども食堂へ寄付する取り組み。
- 生協版GAP…全国の生協が共通して使用している「良い農場づくり」のためのルールブック。組合員に信頼・支持される「たしかな商品」をお届けできるように、食品安全だけでなく、環境保全、労働安全等、農畜水産業の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組み。